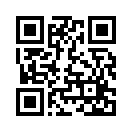2014年05月05日
春日大社

春日大社と言えば石燈籠。参道の両側にずらーっと並んでいます。2月の節分と8月14・15両日の夜、燈籠に灯が入り、いわゆる「万灯篭」(まんとうえ)が幽玄の世界に誘います。

境内では「釣り万燈籠」が暗い部屋で観られる体験コーナーもありました。

萬葉植物園に藤を見に行った帰りに春日大社にもお詣りに行きました。境内でも藤の花が今が盛りでした。

GWだったので各国の観光客をはじめ、結構な人出でした。山門。

偶然、人がいなくなったので本殿を写しましsた。

本殿内では神官が祝詞を上げていました。後で気づくと撮影禁止だった!

本殿横では「大社大杉」」と言う樹齢千年のご神木杉が目を引きました。


本殿の他にも小さな社がたくさんあってそれぞれに由緒があるそうですが、ここでも藤の花が社を取り囲んでました。

社殿を一歩出た横の山肌にも今や藤が真っ盛り。

朱の回廊に釣り燈籠がぶら下がってます。

この釣り燈籠に灯がはいる万燈籠はさぞかし優美で心が洗われることでしょう。

あ・うんの狛犬もさすがに大きい。

春日大社の横には「鹿苑」があり鹿の角きりなどの行事でも有名です。なぜか春日大社のまわりには小鹿が多かった。
2014年04月14日
在原業平
在原業平ゆかりの「不退寺」に行きました。

南都・花の古寺としても有名で、今は業平「椿」が咲き誇っていました。

こじんまりしたお寺ですが、お庭と建物がとてもバランスが良く配置されていて、鶯の声も聞こえていました。

祖父の平城天皇が「薬子の変」に失敗した後、住んだ「萱の御所」だったそうな。天皇の皇子「阿保親王」や孫の業平(825年~880年)もここに住んだそうだ。

古今和歌集の業平の句も境内で見られました。

ちはやぶる 神代もきかず竜田川 からくれないに 水くくるとは 百人一首でも有名な和歌ですね。
六歌仙や三十六歌仙のひとりでもある業平には多くの句があります。

「伊勢物語」の作者でもある業平の句碑の隣にも椿の花が。
から衣 きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思う 句の頭をつなげれば「かきつばた」と詠め、伊勢物語で三河の国・八つ橋で詠んだと言われる。

世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし 「古今集」

裏庭に咲く山桜の花。
名にし負はば いざこと問わぬ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと

咲けば綺麗だろうな、椿のつぼみも膨らむ。
境内では池の周りに色々な花が見られます。

れんぎょうは今が盛りです。

雪やなぎの白とれんぎょうの黄色が混ざりあってます。

真ん中に「業平橋」がかかる中池。
これは花桃かな?燃えてます。

梅の花も咲いてました。


本堂とともに重要文化財に指定されている山門。境内には多宝塔(重文)もあります。
「法輪を転じて退かず」と発願して建てられたのが「不退寺」。

本堂内ではさまざまな重文の仏像も見られます。
本尊は業平自身が作ったと言われる「聖観世音菩薩立像」1m90cmの大きな木彫り一本造の名作です。

春なのに紅葉しているもみじ。


不退寺は近鉄・新大宮(近鉄奈良のひとつ手前)から北へ歩いて15分の丘のふもとにひっそり建っています。
神戸から奈良行き快速急行1本で座っていけるので便利です。
0742-22-5278
http://www3.kcn.ne.jp/~futaiji/

南都・花の古寺としても有名で、今は業平「椿」が咲き誇っていました。

こじんまりしたお寺ですが、お庭と建物がとてもバランスが良く配置されていて、鶯の声も聞こえていました。

祖父の平城天皇が「薬子の変」に失敗した後、住んだ「萱の御所」だったそうな。天皇の皇子「阿保親王」や孫の業平(825年~880年)もここに住んだそうだ。

古今和歌集の業平の句も境内で見られました。

ちはやぶる 神代もきかず竜田川 からくれないに 水くくるとは 百人一首でも有名な和歌ですね。
六歌仙や三十六歌仙のひとりでもある業平には多くの句があります。

「伊勢物語」の作者でもある業平の句碑の隣にも椿の花が。
から衣 きつつなれにし つましあれば はるばるきぬる 旅をしぞ思う 句の頭をつなげれば「かきつばた」と詠め、伊勢物語で三河の国・八つ橋で詠んだと言われる。

世の中に たえて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし 「古今集」

裏庭に咲く山桜の花。
名にし負はば いざこと問わぬ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと

咲けば綺麗だろうな、椿のつぼみも膨らむ。
境内では池の周りに色々な花が見られます。

れんぎょうは今が盛りです。

雪やなぎの白とれんぎょうの黄色が混ざりあってます。

真ん中に「業平橋」がかかる中池。
これは花桃かな?燃えてます。

梅の花も咲いてました。


本堂とともに重要文化財に指定されている山門。境内には多宝塔(重文)もあります。
「法輪を転じて退かず」と発願して建てられたのが「不退寺」。

本堂内ではさまざまな重文の仏像も見られます。
本尊は業平自身が作ったと言われる「聖観世音菩薩立像」1m90cmの大きな木彫り一本造の名作です。

春なのに紅葉しているもみじ。


不退寺は近鉄・新大宮(近鉄奈良のひとつ手前)から北へ歩いて15分の丘のふもとにひっそり建っています。
神戸から奈良行き快速急行1本で座っていけるので便利です。
0742-22-5278
http://www3.kcn.ne.jp/~futaiji/
2014年01月05日
錦天満宮
年始恒例の京都・錦天満宮に初詣に行きました。

この天満宮とは相性が良く、大概の初詣はここで。また京都の繁華街にあるので、錦市場を覗いて歩くのにも便利。近くにホテルも多いので1泊して食べ歩くのにも便利です。今年は錦市場で豆もちを買いました。

天満宮に「牛」はつきもの。受験や厄除けなどの願いを混めて参拝客が撫でるので、頭などはピカピカに輝いてます。
最近、お線香を買いに行くお寺はやはり寺町にある「誓願寺」です。

ここは浄土宗西山深草派の総本山で、大きな阿弥陀如来が通りからも見えます。また、落語の祖「策伝上人」でも有名で、落語発祥のお寺としても知られています。

策伝上人。

堂内には、ひとことだけ願いを書いてお納めする(無料)ひとこと観音も御祭してました。

世阿弥の作とされる謡曲「誓願寺」の舞台にもなってると書いてありました。和泉式部にもゆかりのあるお寺です。

ご近所には京都らしい町屋を改造した「ポールスミス」もあり、それなりに賑わっていました。
京都に行けば立ち寄るのが黄桜の直営店「じろく亭」です。

黄桜の全ての製品が地ビールも含めて揃っていて、おばんざいが美味しい。

お値段も手ごろでメニューも豊富で、カウンターとテーブル席も多く、堀ごたつの団体席もあります。
三条木屋町のビルの4階です。
この天満宮とは相性が良く、大概の初詣はここで。また京都の繁華街にあるので、錦市場を覗いて歩くのにも便利。近くにホテルも多いので1泊して食べ歩くのにも便利です。今年は錦市場で豆もちを買いました。
天満宮に「牛」はつきもの。受験や厄除けなどの願いを混めて参拝客が撫でるので、頭などはピカピカに輝いてます。
最近、お線香を買いに行くお寺はやはり寺町にある「誓願寺」です。
ここは浄土宗西山深草派の総本山で、大きな阿弥陀如来が通りからも見えます。また、落語の祖「策伝上人」でも有名で、落語発祥のお寺としても知られています。
策伝上人。
堂内には、ひとことだけ願いを書いてお納めする(無料)ひとこと観音も御祭してました。
世阿弥の作とされる謡曲「誓願寺」の舞台にもなってると書いてありました。和泉式部にもゆかりのあるお寺です。
ご近所には京都らしい町屋を改造した「ポールスミス」もあり、それなりに賑わっていました。
京都に行けば立ち寄るのが黄桜の直営店「じろく亭」です。
黄桜の全ての製品が地ビールも含めて揃っていて、おばんざいが美味しい。
お値段も手ごろでメニューも豊富で、カウンターとテーブル席も多く、堀ごたつの団体席もあります。
三条木屋町のビルの4階です。
2014年01月04日
初詣は東大寺
千手観音菩薩立像
本来は四月堂に安置される巨像ですが、今は南大門の横の「東大寺ミュージアム」で展示されていました。展示仏像は入替え制なので、ここは見逃しては損です(有料)。
大仏殿は撮影自由。でも瑠遮那仏は大きすぎてもっともらしく写すのは困難です。
大仏さんの右手を守る虚空蔵菩薩。
左手を守る如意輪漢音像。
大仏の右後方の廣目天。
左後方の多聞天。大仏殿の中の仏像はいずれも巨大で見上げるほどのものばかりなので首が痛い。
市内どこからでも見える大仏殿の屋根はさすがに大きく境内も広い。お正月は外国人観光客であふれていました。
入り口の南大門。左右の仁王さんは運慶・快慶の作と言われ、これも巨大。
大仏殿の向かって右には「おびんずるさん」の大きな木像があり、撫でると痛いところが治ると言う。私は時々首が痛くなるけどおびんずるさんの首まで手が届きませんでした。
この日はなぜか寝ている鹿が多く、お正月疲れかな。
大仏殿の中の売店でお線香を買って、次の目的地「興福寺」に向かいました。因みに大仏さんのお線香はとてもいい香りで癒されます。
近くにある「興福寺」の国宝館の館内は国宝のラッシュ。中でもお目当ては「阿修羅像」です。8体並ぶ少年像は全て国宝。ガラスもなく手が届く距離で見られます。
ここはお参りする感覚ではなく「観る」感じて楽しめます。
興福寺・南円堂。
興福寺の境内もとても広く、五重塔をはじめ見所も多い。
初詣でお参りする、と言うより「大仏さんに会いに行く」と言う感覚の初詣でした。神戸からは快速急行1本で座っていけるので奈良は便利です。
2013年12月28日
師走のお参り
お正月を前にお墓参りに行きました。

前回は秋のお彼岸でまだ残暑いっぱいの時。今回は霰も舞い雷もなる寒さ。今年は秋がなく冷房から一気に暖房になったので季節は早い。

お寺の前庭では以前は畝しかなかった場所に水菜や葱や豊かな葉っぱの何か野菜がみずみずしく「食べて食べて」と主張して見事なお寺菜園へと変身してました。

今年の秋に長姉が亡くなり、嫁ぎ先のそのお墓が直ぐご近所と言うのもお参りする側にとっては便利です。おまけに宗派も全く同じ。二つのお寺は普段からお付き合いがあるそうです。

姉のほうのお寺のお庭には見事な市民の木「くろ松」が横へ横へと枝を張り、お庭の立派さではこちらのお寺のほうが上。
これからは二つのお墓にお参りしなければ・・・・。でも一応師走の行事を済ませホッとしました。今夜は美味しいものを食べよう!
前回は秋のお彼岸でまだ残暑いっぱいの時。今回は霰も舞い雷もなる寒さ。今年は秋がなく冷房から一気に暖房になったので季節は早い。
お寺の前庭では以前は畝しかなかった場所に水菜や葱や豊かな葉っぱの何か野菜がみずみずしく「食べて食べて」と主張して見事なお寺菜園へと変身してました。
今年の秋に長姉が亡くなり、嫁ぎ先のそのお墓が直ぐご近所と言うのもお参りする側にとっては便利です。おまけに宗派も全く同じ。二つのお寺は普段からお付き合いがあるそうです。
姉のほうのお寺のお庭には見事な市民の木「くろ松」が横へ横へと枝を張り、お庭の立派さではこちらのお寺のほうが上。
これからは二つのお墓にお参りしなければ・・・・。でも一応師走の行事を済ませホッとしました。今夜は美味しいものを食べよう!
2013年10月14日
高野山
連休の1日、和歌山県の高野山に久しぶりに日帰り旅行しました。

いたるところにユルキャラ「こうやくん」が居ました。
先ずは高野山の定番「奥の院」にお参り。

奥の院は撮影禁止。遠くから見るほかはない。
奥の院には古今の有名武将や企業、慰霊碑が多くあり、見て回る楽しみもあります。
赤穂四十七士の慰霊碑。

阪神・淡路大震災の慰霊碑。

新しいのは「東日本大震災の慰霊碑」です。

奥の院から町の西側にある総本山「金剛峯寺」へ。

金剛峯寺の本殿はとても大きく広い。

なぜか屋根の上には防火用水(?)が乗ってました。

金剛峯寺の内部は拝観出来ます(500円)。見事な襖絵やお庭が素晴らしい。襖絵は撮影禁止。

少し紅葉してたのですが画像では確認できません。

ちょうど鐘楼から時を知らせる梵鐘が聞こえて来て幽玄な雰囲気も・・・。

茶菓を頂きながら大広間の「曼荼羅」も楽しみました。



金剛峯寺の広大な境内のもうひとつの楽しみは「大塔」や「金堂」などの伽藍を拝見することです。
小さな大塔。

高野山といえばこの大きな朱色の大塔です。

残念ながら「金堂」は修理中でした。
書院づくりの伽藍。

午後から出かけたので駆け足の高野山でした。
帰り道は日もとっぷり暮れて梅田で7時半から癒しのお酒を・・。お線香をお土産に買いました。
南海電鉄は橋本までは早いのですが、そこから高野山までは単線で40分以上かかります。そのあたりがまどろっこしい。ただ標高千メートルなので凄い涼しく服装注意です。
皆さんも日ごろの煩悩を減らすために霊山に一度どうぞ。
いたるところにユルキャラ「こうやくん」が居ました。
先ずは高野山の定番「奥の院」にお参り。
奥の院は撮影禁止。遠くから見るほかはない。
奥の院には古今の有名武将や企業、慰霊碑が多くあり、見て回る楽しみもあります。
赤穂四十七士の慰霊碑。
阪神・淡路大震災の慰霊碑。
新しいのは「東日本大震災の慰霊碑」です。
奥の院から町の西側にある総本山「金剛峯寺」へ。
金剛峯寺の本殿はとても大きく広い。
なぜか屋根の上には防火用水(?)が乗ってました。
金剛峯寺の内部は拝観出来ます(500円)。見事な襖絵やお庭が素晴らしい。襖絵は撮影禁止。
少し紅葉してたのですが画像では確認できません。
ちょうど鐘楼から時を知らせる梵鐘が聞こえて来て幽玄な雰囲気も・・・。
茶菓を頂きながら大広間の「曼荼羅」も楽しみました。
金剛峯寺の広大な境内のもうひとつの楽しみは「大塔」や「金堂」などの伽藍を拝見することです。
小さな大塔。
高野山といえばこの大きな朱色の大塔です。
残念ながら「金堂」は修理中でした。
書院づくりの伽藍。
午後から出かけたので駆け足の高野山でした。
帰り道は日もとっぷり暮れて梅田で7時半から癒しのお酒を・・。お線香をお土産に買いました。
南海電鉄は橋本までは早いのですが、そこから高野山までは単線で40分以上かかります。そのあたりがまどろっこしい。ただ標高千メートルなので凄い涼しく服装注意です。
皆さんも日ごろの煩悩を減らすために霊山に一度どうぞ。
2013年09月22日
奈良 白毫寺
奈良市内の白毫寺(びゃくごうじ)に行きました。
「石ばしる垂水の上のさわらびの萌えいずる春になりにけるかも」天智天皇の第七皇子・志貴皇子の離宮跡に建てられたお寺です。

丁度お彼岸中だったので・・彼岸花。

境内には白い彼岸花も。

高台にあるので眺めのいいのと、花の寺として有名です。
ちょうど今は萩の花が見ごろです。

萩の花が石段に咲き乱れて。

白い萩の花もあります。

椿の花や寒桜でも有名らしい。境内にある樹齢400年の「五色椿」

石仏の路には多くの石仏が鎮座。完全な形ではないけど「不動明王」が有名だとか。


苔むした路には点々と石仏が並ぶ。

この丈の低い紫の花はなんでしょうか。

さすがは花の寺、可憐な桔梗の花も咲いていました。

本堂です。

万葉集「笠 金村」(かさのかなむら)の句碑。
「高円の野辺の秋萩いたずらに 咲きか散るらむ見る人なしに」

お寺への入り口には大伴家持の万葉の句も斜め書きにしてありました。

宝蔵には多くの重要文化財の仏像が並び、中央には阿弥陀如来坐像が。

奈良公園の南東の高円山の中腹にあるので、バス亭から約30分の上り坂。着いた時には汗だくだく。それだけに奈良市内一望の見晴らしはさすがの清涼。遠く興福寺の五重塔も眺められます。

展望のいい境内。

ここは「東海自然歩道」にあたるらしく、遠く柳生の里にも続いてるらしい。歩道と言うことは全部歩いて行けというのだろうか、ギャフン!

秋の一日、奈良郊外には実りの稲穂が輝いていました。遠く若草山も見えています。

「石ばしる垂水の上のさわらびの萌えいずる春になりにけるかも」天智天皇の第七皇子・志貴皇子の離宮跡に建てられたお寺です。
丁度お彼岸中だったので・・彼岸花。
境内には白い彼岸花も。
高台にあるので眺めのいいのと、花の寺として有名です。
ちょうど今は萩の花が見ごろです。
萩の花が石段に咲き乱れて。
白い萩の花もあります。
椿の花や寒桜でも有名らしい。境内にある樹齢400年の「五色椿」
石仏の路には多くの石仏が鎮座。完全な形ではないけど「不動明王」が有名だとか。
苔むした路には点々と石仏が並ぶ。
この丈の低い紫の花はなんでしょうか。
さすがは花の寺、可憐な桔梗の花も咲いていました。
本堂です。
万葉集「笠 金村」(かさのかなむら)の句碑。
「高円の野辺の秋萩いたずらに 咲きか散るらむ見る人なしに」
お寺への入り口には大伴家持の万葉の句も斜め書きにしてありました。
宝蔵には多くの重要文化財の仏像が並び、中央には阿弥陀如来坐像が。
奈良公園の南東の高円山の中腹にあるので、バス亭から約30分の上り坂。着いた時には汗だくだく。それだけに奈良市内一望の見晴らしはさすがの清涼。遠く興福寺の五重塔も眺められます。
展望のいい境内。
ここは「東海自然歩道」にあたるらしく、遠く柳生の里にも続いてるらしい。歩道と言うことは全部歩いて行けというのだろうか、ギャフン!
秋の一日、奈良郊外には実りの稲穂が輝いていました。遠く若草山も見えています。
2013年01月03日
初詣
京都の錦天満宮に初詣です。毎年お参りしている相性のいい神社です。

天神さんと言えば「牛」です。頭の神様なので皆が触って頭はつるつるに光っています。

このあたりは南北にお寺が並ぶ寺町です。新京極商店街の間に多くのお寺が見え隠れしています。
TVで紹介されていた落語発祥のお寺「誓願寺」にも寄ってみました。

ご本尊の阿弥陀如来。

お寺の偉い方の説法を伝える中に分かりやすい「笑い」の部分も取り入れたのが落語の始まりだと言われています。
安楽庵策伝上人がその始祖だと言われています。

落語家の参拝も多いそうで、柳家小さん師匠の扇子も飾ってありました。

誓願寺は落語だけではなく広く芸能の神さんで、クラシックから和芸まで、絵馬の代わりに扇子に願掛けが多く見られました。

帰りの四条河原町駅には運よく阪急ご自慢の「京とれいん」が止まっており初めて乗りました。

向かい合った座席は4人用と2人用で和風。いたるところに京風の雰囲気が。座席も広く欧米人でもゆうゆう。土日だけ梅田と河原町を往復しているそうです。車内の意匠にはびっくりさせられました。

天神さんと言えば「牛」です。頭の神様なので皆が触って頭はつるつるに光っています。
このあたりは南北にお寺が並ぶ寺町です。新京極商店街の間に多くのお寺が見え隠れしています。
TVで紹介されていた落語発祥のお寺「誓願寺」にも寄ってみました。
ご本尊の阿弥陀如来。
お寺の偉い方の説法を伝える中に分かりやすい「笑い」の部分も取り入れたのが落語の始まりだと言われています。
安楽庵策伝上人がその始祖だと言われています。
落語家の参拝も多いそうで、柳家小さん師匠の扇子も飾ってありました。
誓願寺は落語だけではなく広く芸能の神さんで、クラシックから和芸まで、絵馬の代わりに扇子に願掛けが多く見られました。
帰りの四条河原町駅には運よく阪急ご自慢の「京とれいん」が止まっており初めて乗りました。
向かい合った座席は4人用と2人用で和風。いたるところに京風の雰囲気が。座席も広く欧米人でもゆうゆう。土日だけ梅田と河原町を往復しているそうです。車内の意匠にはびっくりさせられました。
2012年05月06日
吉野山 金峯山寺
世界遺産・吉野の金峯山寺(きんぷせんじ)の秘仏・ご本尊が公開されているので行きました。

役行者(えんのぎょうじゃ)が祈り出した3体の巨大な青い権現像が公開されています。過去・現在・未来、三世にわたって我々を救済するため憤怒の相で出現したのが「権現」です。
堂内は撮影禁止なのでポスターを撮りました。
金峯山寺には3つの世界遺産があります。
そのひとつ国宝「仁王門」。


1338年に作られた仁王は5.1メートル。阿形と吽形が左右に並んでいます。

世界遺産・金峯山寺の国宝・蔵王堂。大きい!


蔵王堂から境内を見る。

金峯山寺の境内にある南朝宮のあった場所。

1336年、後醍醐天皇が吉野の潜幸して南北朝の対立が始まったとされています。

後醍醐天皇が住んでいたのが世界遺産・吉水神社です。

ここは資料館のようなところで一般公開されています。
後醍醐天皇の玉座。

歌舞伎・義経千本桜でも有名な義経の鎧も公開。案外小柄だったみたいです。

義経が静御前と涙の別れをしたというお話で、一目千本の桜が見渡せる吉水神社。今は新緑が見えるだけでした。

ここは秀吉も桜を楽しんだ場所でした。

吉水神社から谷をへだてた金峯山寺・大きな蔵王堂が見えます。

金峯山寺の開祖・役行者も吉水神社では見られます。

吉野は山の峰にずーっと道がついていて両側には土産もの屋や宿泊所が並んでいます。相当アップダウンがあります。
吉野のくず餅・黄な粉に黒蜜をかけて一休みしました。

みやまきりしまが綺麗です。

宿坊「桜本坊」(さくらもとぼう)の山門には赤い仁王が並んでました。

お庭が綺麗というので宿坊「竹林院」にも行きました。


竹林院の本坊。でも宿坊で泊まると夜が退屈しそうですね。

吉野山へは近鉄・阿部野橋から特急で1時間20分。30分ごとに出ています。
近鉄吉野駅。

駅前からは日本最古のロープーウェイが短い距離を登っています。

金峯山寺から竹林院までは登り坂が多いので、逆に駅前からバスで「中千本」行きに乗り、奥から逆に金峯山寺へ下るのがおすすめです。快晴の中、この日は1万歩、歩きました。
金峯山寺 http://www.kinpusen.or.jp/
それでも巨大な3体の青い金剛蔵王権現像はまじかに拝観できるので凄い迫力で迫って来ました。

役行者(えんのぎょうじゃ)が祈り出した3体の巨大な青い権現像が公開されています。過去・現在・未来、三世にわたって我々を救済するため憤怒の相で出現したのが「権現」です。
堂内は撮影禁止なのでポスターを撮りました。
金峯山寺には3つの世界遺産があります。
そのひとつ国宝「仁王門」。
1338年に作られた仁王は5.1メートル。阿形と吽形が左右に並んでいます。
世界遺産・金峯山寺の国宝・蔵王堂。大きい!
蔵王堂から境内を見る。
金峯山寺の境内にある南朝宮のあった場所。
1336年、後醍醐天皇が吉野の潜幸して南北朝の対立が始まったとされています。
後醍醐天皇が住んでいたのが世界遺産・吉水神社です。
ここは資料館のようなところで一般公開されています。
後醍醐天皇の玉座。
歌舞伎・義経千本桜でも有名な義経の鎧も公開。案外小柄だったみたいです。
義経が静御前と涙の別れをしたというお話で、一目千本の桜が見渡せる吉水神社。今は新緑が見えるだけでした。
ここは秀吉も桜を楽しんだ場所でした。
吉水神社から谷をへだてた金峯山寺・大きな蔵王堂が見えます。
金峯山寺の開祖・役行者も吉水神社では見られます。
吉野は山の峰にずーっと道がついていて両側には土産もの屋や宿泊所が並んでいます。相当アップダウンがあります。
吉野のくず餅・黄な粉に黒蜜をかけて一休みしました。
みやまきりしまが綺麗です。
宿坊「桜本坊」(さくらもとぼう)の山門には赤い仁王が並んでました。
お庭が綺麗というので宿坊「竹林院」にも行きました。
竹林院の本坊。でも宿坊で泊まると夜が退屈しそうですね。
吉野山へは近鉄・阿部野橋から特急で1時間20分。30分ごとに出ています。
近鉄吉野駅。
駅前からは日本最古のロープーウェイが短い距離を登っています。
金峯山寺から竹林院までは登り坂が多いので、逆に駅前からバスで「中千本」行きに乗り、奥から逆に金峯山寺へ下るのがおすすめです。快晴の中、この日は1万歩、歩きました。
金峯山寺 http://www.kinpusen.or.jp/
それでも巨大な3体の青い金剛蔵王権現像はまじかに拝観できるので凄い迫力で迫って来ました。

2011年11月07日
吉備路を行く
岡山市の北、いわゆる吉備路に初めて行きました。
以前から「吉備津神社」には行きたかったのです。

岡山駅から吉備線と言う支線が出ていて割りに近いところにあります。
山門から本殿へは急な階段が。


吉備津神社の本殿は「国宝」です。

山の裾野にある境内はかなり広く、長い回廊で末社とつながっています。
回廊の中。


本殿と回廊の関係はこのようになっています。
ちょうど「七・五・三」の時期で、結構子ども連れの家族も大勢いました。
慣れない着物姿で裾を踏んで転んだ娘を父親が泥を払ってる微笑ましい姿も。

境内の大銀杏の木も丁度色づいて。

境内にある智恵や学問・受験の神様「一台社」

おみくじで合格祈願です。

桃太郎伝説のあるのが吉備津神社。ちゃんと鬼退治伝説も有り、ちなんだ社や旧跡もあります。

備中神楽面の一式。
境内には水の流れていない水車小屋もありました。

生憎のお天気でしたが、刈り取られずに放置された稲の向こうに本殿が幻想的な姿で見えていました。

神主さんに聞いて驚いたのですが、吉備津神社は3つあると言う。
備前の国にあるのが「吉備津彦神社」。備中にあるのが「吉備津神社」。そして福山の備後の国にも吉備津神社があると言う。
備前と備中は昔の国境を挟んであまりに近くにあるため、備前を彦神社にしたそうです。
直ぐ近くなので「吉備津彦神社」にも行きました。

吉備津神社の大銀杏の木に代わり、彦神社では平安杉がご神木として葉をつけていました。

こちらの本殿は国宝ではありません。

第七代孝霊天皇の第三皇子・大吉備津彦命が主祭神と言うから、確かに古代ゆかりの神社です。

本殿の内部。
さて、ここまで来たからにはと、風土記の丘にある備中国分寺まで足を延ばしました。
コスモスと五重塔。

柿食えば鐘がなるなり法隆寺・・・にも国宝・五重塔がありますが、国分寺の五重塔は重要文化財でした。
でも、きっちり実った柿が迎えてくれました。


備中国分寺の山号は「日照山国分寺」です。
まだ時間があったので、日本の三大稲荷と言われる「最上稲荷」(さいじょういなり)にも寄りました。

「伏見」「豊川」と並ぶ稲荷だけに再建された本殿は見上げるほど大きく、初詣や節分には押すな押すなの人がお参りするそうです。岡山で第一の人気だそうです。
でも昔の本殿のほうが雰囲気はありました。

こちらの稲荷の起源は1200年前。明治には神仏習合が許されたという特別な稲荷で、お寺でありながら高さ27mの大鳥居が
随分手前の平野に突然建って現れ驚かされます。
旧・本殿への登り道には、七十七の末社の碑が並び、いろんなご利益を詠っています。

そのお社版も旧本殿の周りには並んでいました。

でも「稲荷」だから、やっぱり狛犬ではなく「狐」でした。

吉備津神社 http://kibitujinja.com/
吉備津彦神社 http://www.kibitsuhiko.or.jp/
備中国分寺 http://www.city.soja.okayama.jp/kanko/kankochi/kokubunji.jsp
最上稲荷 http://www.inari.ne.jp/
以前から「吉備津神社」には行きたかったのです。
岡山駅から吉備線と言う支線が出ていて割りに近いところにあります。
山門から本殿へは急な階段が。

吉備津神社の本殿は「国宝」です。
山の裾野にある境内はかなり広く、長い回廊で末社とつながっています。
回廊の中。

本殿と回廊の関係はこのようになっています。
ちょうど「七・五・三」の時期で、結構子ども連れの家族も大勢いました。
慣れない着物姿で裾を踏んで転んだ娘を父親が泥を払ってる微笑ましい姿も。
境内の大銀杏の木も丁度色づいて。
境内にある智恵や学問・受験の神様「一台社」
おみくじで合格祈願です。
桃太郎伝説のあるのが吉備津神社。ちゃんと鬼退治伝説も有り、ちなんだ社や旧跡もあります。
備中神楽面の一式。
境内には水の流れていない水車小屋もありました。

生憎のお天気でしたが、刈り取られずに放置された稲の向こうに本殿が幻想的な姿で見えていました。
神主さんに聞いて驚いたのですが、吉備津神社は3つあると言う。
備前の国にあるのが「吉備津彦神社」。備中にあるのが「吉備津神社」。そして福山の備後の国にも吉備津神社があると言う。
備前と備中は昔の国境を挟んであまりに近くにあるため、備前を彦神社にしたそうです。
直ぐ近くなので「吉備津彦神社」にも行きました。
吉備津神社の大銀杏の木に代わり、彦神社では平安杉がご神木として葉をつけていました。
こちらの本殿は国宝ではありません。
第七代孝霊天皇の第三皇子・大吉備津彦命が主祭神と言うから、確かに古代ゆかりの神社です。
本殿の内部。
さて、ここまで来たからにはと、風土記の丘にある備中国分寺まで足を延ばしました。
コスモスと五重塔。
柿食えば鐘がなるなり法隆寺・・・にも国宝・五重塔がありますが、国分寺の五重塔は重要文化財でした。
でも、きっちり実った柿が迎えてくれました。
備中国分寺の山号は「日照山国分寺」です。
まだ時間があったので、日本の三大稲荷と言われる「最上稲荷」(さいじょういなり)にも寄りました。
「伏見」「豊川」と並ぶ稲荷だけに再建された本殿は見上げるほど大きく、初詣や節分には押すな押すなの人がお参りするそうです。岡山で第一の人気だそうです。
でも昔の本殿のほうが雰囲気はありました。
こちらの稲荷の起源は1200年前。明治には神仏習合が許されたという特別な稲荷で、お寺でありながら高さ27mの大鳥居が
随分手前の平野に突然建って現れ驚かされます。
旧・本殿への登り道には、七十七の末社の碑が並び、いろんなご利益を詠っています。
そのお社版も旧本殿の周りには並んでいました。
でも「稲荷」だから、やっぱり狛犬ではなく「狐」でした。
吉備津神社 http://kibitujinja.com/
吉備津彦神社 http://www.kibitsuhiko.or.jp/
備中国分寺 http://www.city.soja.okayama.jp/kanko/kankochi/kokubunji.jsp
最上稲荷 http://www.inari.ne.jp/
2011年09月03日
水間寺
水間寺(通称 水間観音)に行きました。

南海電車「貝塚」駅に隣接する水間鉄道「貝塚」駅にはひまわりのバックに看板が出ていました。
貝塚から単線・2両編成の水間鉄道で15分くらい。
終着の「水間観音駅」

駅から徒歩で500m。ま新しい「太鼓橋」が迎えてくれます。

大阪府下唯一の三重塔と本堂です。

貝塚市にある水間寺は、天台宗別格本山。山号は龍谷山。本尊は聖観世音菩薩。

729年~天平年間に聖武天皇の勅願を受けて行基が開創したと伝えられています。

大規模でもなく小規模でもなく、ほどよい境内の広さ。梵鐘もあります。

ご本尊ではないけれど境内には大きな観音さまの像がありました。

境内の両面はこ綺麗な渓流が。

昔は1輌編成で趣きのある水間鉄道には鉄道ファンも多く、今は、終着駅に昔の車輌が鎮座していました。
単線の風情は今も残っています。


水間観音 この方の案内が分かりやすい。 http://www.y-morimoto.com/s_saigoku/s_saigoku04.html
南海電車「貝塚」駅に隣接する水間鉄道「貝塚」駅にはひまわりのバックに看板が出ていました。
貝塚から単線・2両編成の水間鉄道で15分くらい。
終着の「水間観音駅」
駅から徒歩で500m。ま新しい「太鼓橋」が迎えてくれます。
大阪府下唯一の三重塔と本堂です。
貝塚市にある水間寺は、天台宗別格本山。山号は龍谷山。本尊は聖観世音菩薩。
729年~天平年間に聖武天皇の勅願を受けて行基が開創したと伝えられています。
大規模でもなく小規模でもなく、ほどよい境内の広さ。梵鐘もあります。
ご本尊ではないけれど境内には大きな観音さまの像がありました。
境内の両面はこ綺麗な渓流が。
昔は1輌編成で趣きのある水間鉄道には鉄道ファンも多く、今は、終着駅に昔の車輌が鎮座していました。
単線の風情は今も残っています。
水間観音 この方の案内が分かりやすい。 http://www.y-morimoto.com/s_saigoku/s_saigoku04.html
2011年01月11日
十日戎
新装なった神戸「柳原のえべっさん」に行くべきところを、つい便利な西宮神社の十日戎に行ってしまいました。
えべっさんにお参りするのは初めてです。

えべっさんはお商売している方が行くもの、と思ってたので今まで1度も行ってなかったのです。
ところがどうしてどうして、誰もがお祭り気分でお参りしている賑わい。
驚きました。

阪神西宮駅から神社までは、屋台や出店がぎっしり。人出もぎっしり。
やっと鳥居までたどり着きました。

昨年のお札やお飾りを返却する場所が2ヶ所。大規模な「燃えるゴミ」置き場のよう。
なかなか進まない列に並ぶこと20分あまり、ようやく本殿にたどり着きました。

右と左に「お祓い」をする人がひとりづつ、皆、頭を祓ってもらいたいので、ここもまた行列。

ようやく神殿に。
さすがに数ある戎神社の発生・本家だけに風格あるお社です。
この下にお賽銭箱があり、遠くから硬貨を投げる人が多いので、最前列の人は当たって「痛い!」だろうな。

神殿左側には西宮戎だけの特徴らしい本物の「大まぐろ」が奉ってあり、なぜか硬貨がベタベタ。

誰がどのように食べるのだろう。
本殿を出るとお目当ての「お札・お守り・おみくじ」と「福笹」売場。

商売繁盛!笹持って来い!
綺麗な福娘が福笹を売っていました。一番安くて¥1,000.

広い境内は「お店」「屋台」「縁起もの」を売る店が所狭しと並んで、参拝者のお祭り気分を煽ります。

いやはや、こんなに大規模で華やかな十日戎だとは思っても見ませんでした。
大阪の今宮戎になると狭い境内はもっと混雑してるのだろうか。
手足が冷え切り、熱燗が恋しくなりました。
もちろん帰りに飲みました、が。
えべっさんにお参りするのは初めてです。
えべっさんはお商売している方が行くもの、と思ってたので今まで1度も行ってなかったのです。
ところがどうしてどうして、誰もがお祭り気分でお参りしている賑わい。
驚きました。
阪神西宮駅から神社までは、屋台や出店がぎっしり。人出もぎっしり。
やっと鳥居までたどり着きました。
昨年のお札やお飾りを返却する場所が2ヶ所。大規模な「燃えるゴミ」置き場のよう。
なかなか進まない列に並ぶこと20分あまり、ようやく本殿にたどり着きました。
右と左に「お祓い」をする人がひとりづつ、皆、頭を祓ってもらいたいので、ここもまた行列。
ようやく神殿に。
さすがに数ある戎神社の発生・本家だけに風格あるお社です。
この下にお賽銭箱があり、遠くから硬貨を投げる人が多いので、最前列の人は当たって「痛い!」だろうな。
神殿左側には西宮戎だけの特徴らしい本物の「大まぐろ」が奉ってあり、なぜか硬貨がベタベタ。
誰がどのように食べるのだろう。
本殿を出るとお目当ての「お札・お守り・おみくじ」と「福笹」売場。
商売繁盛!笹持って来い!
綺麗な福娘が福笹を売っていました。一番安くて¥1,000.
広い境内は「お店」「屋台」「縁起もの」を売る店が所狭しと並んで、参拝者のお祭り気分を煽ります。
いやはや、こんなに大規模で華やかな十日戎だとは思っても見ませんでした。
大阪の今宮戎になると狭い境内はもっと混雑してるのだろうか。
手足が冷え切り、熱燗が恋しくなりました。
もちろん帰りに飲みました、が。
2010年08月16日
龍安寺
湿度が90%はあろうかと言う日に、石庭で有名な京都・龍安寺に行きました。

石庭・左半分

石庭・右半分
世界文化遺産に登録されている龍安寺は、お盆休みのせいもあり、
世界中から観光客が集まっていました。

石庭前の広い縁側も超満員。
随分前に来た時はゆっくり座って鑑賞できたのですが、
今回は暑いのと混雑してるのとで、早々に引き上げました。
なにせ、じっとしていても頭から滂沱の汗。
「心頭滅却すれば火も亦た涼し」とは龍安寺と同じ臨済宗・妙心寺派の教えだが、
凡人には火はやはり熱いのだ!冷えたビールが欲しい!
イタリア青年のシャツの背中が汗でぐっしょり。背中の筋肉も透けて丸見えって感じ。
誰も彼も夏の京都の湿度には「うんざり」した表情でした。
それにしても欧米の観光客の多さよ。金閣寺まで徒歩で行ける距離なので、ついで見学が多いのでしょう。
私はバスで1停留所の「堂本印象」美術館から徒歩で来ましたが。

昔はおしどりがたくさん泳いでいたからと「おしどり池」は緑の水面に蓮がいっぱい。
午後3時には花が閉じてしまうので開花してるところは見られませんでしたが、
朝ならさぞ綺麗だったでしょう。
正式には「鏡容池」と呼ぶそうですが、龍安寺のもうひとつの見どころです。
楓の木が池の周りにいっぱいあるので、秋はさぞかし錦秋模様が楽しめることでしょう。
蒸し暑くもないしね。
鉢植えの蓮の蕾。

それでも咲き誇る蓮の花を見つけました。

大雲山「龍安寺」 HP http://www.ryoanji.jp/
石庭・左半分
石庭・右半分
世界文化遺産に登録されている龍安寺は、お盆休みのせいもあり、
世界中から観光客が集まっていました。
石庭前の広い縁側も超満員。
随分前に来た時はゆっくり座って鑑賞できたのですが、
今回は暑いのと混雑してるのとで、早々に引き上げました。
なにせ、じっとしていても頭から滂沱の汗。
「心頭滅却すれば火も亦た涼し」とは龍安寺と同じ臨済宗・妙心寺派の教えだが、
凡人には火はやはり熱いのだ!冷えたビールが欲しい!
イタリア青年のシャツの背中が汗でぐっしょり。背中の筋肉も透けて丸見えって感じ。
誰も彼も夏の京都の湿度には「うんざり」した表情でした。
それにしても欧米の観光客の多さよ。金閣寺まで徒歩で行ける距離なので、ついで見学が多いのでしょう。
私はバスで1停留所の「堂本印象」美術館から徒歩で来ましたが。
昔はおしどりがたくさん泳いでいたからと「おしどり池」は緑の水面に蓮がいっぱい。
午後3時には花が閉じてしまうので開花してるところは見られませんでしたが、
朝ならさぞ綺麗だったでしょう。
正式には「鏡容池」と呼ぶそうですが、龍安寺のもうひとつの見どころです。
楓の木が池の周りにいっぱいあるので、秋はさぞかし錦秋模様が楽しめることでしょう。
蒸し暑くもないしね。
鉢植えの蓮の蕾。
それでも咲き誇る蓮の花を見つけました。
大雲山「龍安寺」 HP http://www.ryoanji.jp/
2010年03月12日
阿修羅が観られる
3月1日に奈良・興福寺の国宝館が新装オープン!あの阿修羅像が直ぐそばで観られるようになりました。
東京・福岡・奈良の「阿修羅展」の過熱ブームは何だったのでしょう・・・と言う観やすさでした。

国宝の宝庫「国宝館」は、以前から観られた様々な素晴らしい仏像群に今回から「八部衆像」が加わり、ライティングや陳列にも工夫が見られ随分観やすくなっていました。


阿修羅像を中心に左右に3体づつ。7体の「八部衆」のうち少年は4体、表情が新鮮です。
「五部浄」像だけが胴体がないので、顔が隣のガラスケースに陳列されていますが、7体の国宝「八部衆像」は、そこだけ別世界のようで、奈良・天平時代にタイム・スリップ!同じ寸法の7体が居並ぶ光景に興奮とため息・・・でした。


興福寺・国宝館は年中無休。¥600
平日でも観光バスの2~3台は来てますが、待ち時間なく入館出来て拝観も楽に出来ます。
関西の春は「お水取り」から。
奈良国立博物館では二月堂の「お水取り行事」(修二会)展も開催されていました。


阪神なんば線の開通から1年。奈良には座ったまま直行できる便利さで、乗客も増えてるそうです。

奈良県は平城遷都1300年祭が今年10月末まで開催され、季節ごとに公開される秘仏もあちこちの神社・仏閣で見られます。。
ぽかぽか陽気になればぜひ散策を兼ねて奈良を訪れて下さい。

東京・福岡・奈良の「阿修羅展」の過熱ブームは何だったのでしょう・・・と言う観やすさでした。
国宝の宝庫「国宝館」は、以前から観られた様々な素晴らしい仏像群に今回から「八部衆像」が加わり、ライティングや陳列にも工夫が見られ随分観やすくなっていました。
阿修羅像を中心に左右に3体づつ。7体の「八部衆」のうち少年は4体、表情が新鮮です。
「五部浄」像だけが胴体がないので、顔が隣のガラスケースに陳列されていますが、7体の国宝「八部衆像」は、そこだけ別世界のようで、奈良・天平時代にタイム・スリップ!同じ寸法の7体が居並ぶ光景に興奮とため息・・・でした。
興福寺・国宝館は年中無休。¥600
平日でも観光バスの2~3台は来てますが、待ち時間なく入館出来て拝観も楽に出来ます。
関西の春は「お水取り」から。
奈良国立博物館では二月堂の「お水取り行事」(修二会)展も開催されていました。
阪神なんば線の開通から1年。奈良には座ったまま直行できる便利さで、乗客も増えてるそうです。
奈良県は平城遷都1300年祭が今年10月末まで開催され、季節ごとに公開される秘仏もあちこちの神社・仏閣で見られます。。
ぽかぽか陽気になればぜひ散策を兼ねて奈良を訪れて下さい。
2010年01月01日
2010初詣
奈良は寺の町。近所の小さなお寺で突く「除夜の鐘」を聞きながら、いつのまにか眠ってしまってました。

薬師寺・西塔 東塔はすっぽり網をかぶって復元工事中、見られません。
薬師寺といえば、白鳳時代の国宝「薬師三尊像」が有名です。
日光・月光菩薩の中央に鎮座する薬師如来の前では、僧侶たちが新年の祈りを捧げていて、お堂(金堂)の中は立錐の余地もないほどでした。お正月から15日までは薬師如来像の前で「国宝・吉祥天女画像」も公開されています。

中央の薬師如来像。
薬師三尊像が並ぶ金堂。

薬師寺の中門には極彩色の金剛力士像(仁王さん)がお寺をお守りしてました。


薬師寺管主・山田法胤さんのありがたい年頭の法話も聞けました。
今年は「庚寅(かのえとら)」年。行き詰った結果、自ら新しいものに動き始め生まれ出る年、らしい。

平城遷都1,300年に当たる今年、薬師寺のもうひとつの見ものは、先日亡くなった平山郁夫画伯の「大唐西域壁画」が見られることです。
境内の北部にある「玄奘三蔵院・伽藍」の壁画院で見られます。

玄奘塔の正面には「不東」の額がかかってます。これは中国から一大決心で西域へ経典を求めて旅したからには「もう二度と東の中国には戻らないぞ」と言う玄奘三蔵法師の心を「不東」と言う文字で表しているそうです。

お正月は普段見られない僧侶の姿も境内で良く見かけます。

薬師寺公式HP http://www.nara-yakushiji.com/
そして、奈良の初詣といえば、やはりここ「東大寺」は、はずせません。
お馴染みの大仏さんにもご挨拶しなきゃ、です。

元日なのに中国・韓国からのお客も含めてかなりの団体客で賑わってました。
貫禄の大建築・南大門の額は「大華厳寺」

お馴染みの仁王さん、金剛力士像は「運慶・快慶」の作です。


とにかく寒くて冷え切った奈良の元日、お寺は暖房もなく「身が引き締まる」どころでは有りませんでした。
鹿たちも座り込んで草を暖めて?ました。

薬師寺・西塔 東塔はすっぽり網をかぶって復元工事中、見られません。
薬師寺といえば、白鳳時代の国宝「薬師三尊像」が有名です。
日光・月光菩薩の中央に鎮座する薬師如来の前では、僧侶たちが新年の祈りを捧げていて、お堂(金堂)の中は立錐の余地もないほどでした。お正月から15日までは薬師如来像の前で「国宝・吉祥天女画像」も公開されています。
中央の薬師如来像。
薬師三尊像が並ぶ金堂。
薬師寺の中門には極彩色の金剛力士像(仁王さん)がお寺をお守りしてました。
薬師寺管主・山田法胤さんのありがたい年頭の法話も聞けました。
今年は「庚寅(かのえとら)」年。行き詰った結果、自ら新しいものに動き始め生まれ出る年、らしい。
平城遷都1,300年に当たる今年、薬師寺のもうひとつの見ものは、先日亡くなった平山郁夫画伯の「大唐西域壁画」が見られることです。
境内の北部にある「玄奘三蔵院・伽藍」の壁画院で見られます。
玄奘塔の正面には「不東」の額がかかってます。これは中国から一大決心で西域へ経典を求めて旅したからには「もう二度と東の中国には戻らないぞ」と言う玄奘三蔵法師の心を「不東」と言う文字で表しているそうです。
お正月は普段見られない僧侶の姿も境内で良く見かけます。
薬師寺公式HP http://www.nara-yakushiji.com/
そして、奈良の初詣といえば、やはりここ「東大寺」は、はずせません。
お馴染みの大仏さんにもご挨拶しなきゃ、です。
元日なのに中国・韓国からのお客も含めてかなりの団体客で賑わってました。
貫禄の大建築・南大門の額は「大華厳寺」
お馴染みの仁王さん、金剛力士像は「運慶・快慶」の作です。
とにかく寒くて冷え切った奈良の元日、お寺は暖房もなく「身が引き締まる」どころでは有りませんでした。
鹿たちも座り込んで草を暖めて?ました。
2009年12月02日
東福寺
12月の紅葉は、盛りを過ぎたとは言うものの、こんなに大規模な錦が迎えてくれるとは思ってもみませんでした。噂に違わぬ東福寺の紅葉!
重森三玲のモダンな作庭もたっぷりどうぞ。

鎌倉時代に関白・藤原道家が菩提寺として造営した「東福寺」は、奈良の「東大寺」と「興福寺」から一文字づつ貰って名づけたと言います。境内の「通天橋」は紅葉の名所として人気があり、12月だと言うのにさすが観光名所、人並みが続いてました。

屋根付き回廊「通天橋」からの眺めです。




通天橋を渡ると「開山堂」に到着。

珍しい楼閣「伝衣閣(でんねかく)」。
江戸時代の名園が前庭にあります。

東福寺・経蔵。

国宝の「三門」。

東福寺のもうひとつの国宝は「龍吟庵(りょうぎんあん)」。
日本最古(室町時代)の方丈建築で足利義満直筆の「扁額」が迎えてくれます。

龍吟庵には「通天橋」と同じ様式の「偃月橋(えんげつきょう)」を渡って行きます。

作庭家・重森三玲(しげもり みれい)1896~1975
東福寺の「方丈」と「龍吟庵」には、重森三玲のモダンな作庭が見られます。

「龍吟庵」の西庭「龍の庭」。


東庭「不離の庭」。

南庭「無の庭」。

「無の庭」と「龍の庭」とは「稲妻」を表現した塀で仕切られています。

いずれも昭和39年の作。
室町時代の国宝を取り巻く庭としても不思議にマッチして違和感がないのに驚きます。
もうひとつ、重森三玲の作庭が見られるのが「方丈」を囲む「八相の庭」です。
こちらは昭和14年の作です。
「井田市松の庭」。

「小市松の庭」。

石の「北斗七星の庭」。

そして、210坪の枯山水「南庭」。


「通天橋」「龍吟庵」「方丈」いすれも入場料¥400を取られるのが、ちょっと残念!
紅葉の季節でなければ通天橋は無料だとか。


臨済宗 大本山「東福寺」 http://www.tofukuji.jp/index2.html 075-561-0087
JR奈良線「東福寺」 京都の次の駅
京阪「東福寺」 下車 徒歩10分
周囲に多くの「院」や「庵」を持つ大伽藍です。

重森三玲のモダンな作庭もたっぷりどうぞ。
鎌倉時代に関白・藤原道家が菩提寺として造営した「東福寺」は、奈良の「東大寺」と「興福寺」から一文字づつ貰って名づけたと言います。境内の「通天橋」は紅葉の名所として人気があり、12月だと言うのにさすが観光名所、人並みが続いてました。
屋根付き回廊「通天橋」からの眺めです。
通天橋を渡ると「開山堂」に到着。
珍しい楼閣「伝衣閣(でんねかく)」。
江戸時代の名園が前庭にあります。
東福寺・経蔵。
国宝の「三門」。
東福寺のもうひとつの国宝は「龍吟庵(りょうぎんあん)」。
日本最古(室町時代)の方丈建築で足利義満直筆の「扁額」が迎えてくれます。
龍吟庵には「通天橋」と同じ様式の「偃月橋(えんげつきょう)」を渡って行きます。
作庭家・重森三玲(しげもり みれい)1896~1975
東福寺の「方丈」と「龍吟庵」には、重森三玲のモダンな作庭が見られます。
「龍吟庵」の西庭「龍の庭」。
東庭「不離の庭」。
南庭「無の庭」。
「無の庭」と「龍の庭」とは「稲妻」を表現した塀で仕切られています。
いずれも昭和39年の作。
室町時代の国宝を取り巻く庭としても不思議にマッチして違和感がないのに驚きます。
もうひとつ、重森三玲の作庭が見られるのが「方丈」を囲む「八相の庭」です。
こちらは昭和14年の作です。
「井田市松の庭」。
「小市松の庭」。
石の「北斗七星の庭」。
そして、210坪の枯山水「南庭」。
「通天橋」「龍吟庵」「方丈」いすれも入場料¥400を取られるのが、ちょっと残念!
紅葉の季節でなければ通天橋は無料だとか。
臨済宗 大本山「東福寺」 http://www.tofukuji.jp/index2.html 075-561-0087
JR奈良線「東福寺」 京都の次の駅
京阪「東福寺」 下車 徒歩10分
周囲に多くの「院」や「庵」を持つ大伽藍です。
2009年11月16日
紅葉の円成寺
奈良 忍辱山・円成寺 (にんにくせん えんじょうじ)に行って来ました。
小さなお寺ながら紅葉が綺麗だと聞いていたからです。

近鉄奈良からバスの便も少ないからでしょうか。見ごろだと言うのに観光客の姿もあまりありませんでした。

円成寺の特徴は、浄瑠璃寺と同じように、浄土式・舟遊式を兼備した平安時代様式の庭園です。


あまり多くはないのですが、国宝と重要文化財もあります。

二つの国宝のうちの一つ、多宝塔に安置された「大日如来坐像」あの運慶の作品です。

これほど装飾が綺麗な多宝塔も珍しいと言われています。

そして、もうひとつの国宝。全国最古で全国最小の国宝建造物、春日大社造営のモデルになった春日造社殿「春日堂と白山堂」


円成寺・本堂には重文「阿弥陀如来像」「四天王像」「聖徳太子二歳像」などがあります。

池の正面の「楼門」は堂々とした佇まいで、入母屋桧皮葺。
楼門は近くで見ると、格式の高い「三手先」や「花肘木」などの建築様式が見事です。

池の回りには「茶店」があり、冷えた身体には暖かい食べ物が・・・。

東入り口にある素朴な「勧請縄(かんじょうなわ)」。
1月10日に松の木に揚げられたもので、少し古びていました。


円成寺へは近鉄奈良駅から奈良交通バス 柳生方面4番乗り場。
30分「忍辱山」下車。
円成寺 0742-93-0353
紅葉の時期には臨時便も出ます。
今年の紅葉を堪能しました。

小さなお寺ながら紅葉が綺麗だと聞いていたからです。
近鉄奈良からバスの便も少ないからでしょうか。見ごろだと言うのに観光客の姿もあまりありませんでした。
円成寺の特徴は、浄瑠璃寺と同じように、浄土式・舟遊式を兼備した平安時代様式の庭園です。
あまり多くはないのですが、国宝と重要文化財もあります。
二つの国宝のうちの一つ、多宝塔に安置された「大日如来坐像」あの運慶の作品です。
これほど装飾が綺麗な多宝塔も珍しいと言われています。
そして、もうひとつの国宝。全国最古で全国最小の国宝建造物、春日大社造営のモデルになった春日造社殿「春日堂と白山堂」
円成寺・本堂には重文「阿弥陀如来像」「四天王像」「聖徳太子二歳像」などがあります。
池の正面の「楼門」は堂々とした佇まいで、入母屋桧皮葺。
楼門は近くで見ると、格式の高い「三手先」や「花肘木」などの建築様式が見事です。
池の回りには「茶店」があり、冷えた身体には暖かい食べ物が・・・。
東入り口にある素朴な「勧請縄(かんじょうなわ)」。
1月10日に松の木に揚げられたもので、少し古びていました。
円成寺へは近鉄奈良駅から奈良交通バス 柳生方面4番乗り場。
30分「忍辱山」下車。
円成寺 0742-93-0353
紅葉の時期には臨時便も出ます。
今年の紅葉を堪能しました。
2009年07月26日
浄瑠璃寺
確か高校生の時に、堀辰雄の「浄瑠璃寺の春」と言う短編を読んで「行ってみよう」と、友だちと一度行った記憶があるのが奈良の浄瑠璃寺。
「浄瑠璃寺の春」http://homepage2.nifty.com/kodairoad/sakusaku/1_11-2.htm
短編では「馬酔木」(あしび)の寺として紹介されていて、前回は丁度「馬酔木」が咲いていたような記憶があるが、何せ数十年前のこと。先日訪れた時は、花菖蒲も終わり,紫陽花も枯れかけで、僅かに「百合」や「桔梗」が池の回りに可憐に咲いていただけ。


堀辰雄夫妻は奈良から浄瑠璃寺まで歩いて行ったようだが、今は近鉄奈良駅から直通バスで25分。1日数本しか出ていないので要確認(奈良交通バス)。また、JR加茂駅から岩船神社などを回る循環バスも運行されている。

真言律宗 小田原山「浄瑠璃寺」 九体阿弥陀堂
この寺では薬師仏をまつる東の三重塔(国宝)に苦悩の救済を願い、中央の池を周り、九体の阿弥陀如来像(国宝)が安置されている阿弥陀堂(国宝)に西方浄土への来迎を願うのが、お参りの方法とされています。

紅葉の頃はさぞかし!と思われる三重塔。

大きな九体の阿弥陀如来坐像も見事で、その四隅には国宝の四天王像も守護をしています。
九体寺と言う別名も持つ「浄瑠璃寺」は奈良のお寺とは言うものの、行政的には京都府・木津川市にあります。
山に囲まれた鄙びた里にひっそりとした佇まいで建っているのは昔も今も同じです。

山門までの道には萩の木が植えられ、多分もう少しで満開になるのでしょう。

中央の宝池を一周すると「鐘楼」や「石仏」たちもひっそりと木陰に隠れるように迎えてくれます。

浄瑠璃寺はJR奈良・近鉄奈良からも直行バスがありますが、JR加茂駅からも循環バスが出ています。

「浄瑠璃寺の春」http://homepage2.nifty.com/kodairoad/sakusaku/1_11-2.htm
短編では「馬酔木」(あしび)の寺として紹介されていて、前回は丁度「馬酔木」が咲いていたような記憶があるが、何せ数十年前のこと。先日訪れた時は、花菖蒲も終わり,紫陽花も枯れかけで、僅かに「百合」や「桔梗」が池の回りに可憐に咲いていただけ。

堀辰雄夫妻は奈良から浄瑠璃寺まで歩いて行ったようだが、今は近鉄奈良駅から直通バスで25分。1日数本しか出ていないので要確認(奈良交通バス)。また、JR加茂駅から岩船神社などを回る循環バスも運行されている。
真言律宗 小田原山「浄瑠璃寺」 九体阿弥陀堂
この寺では薬師仏をまつる東の三重塔(国宝)に苦悩の救済を願い、中央の池を周り、九体の阿弥陀如来像(国宝)が安置されている阿弥陀堂(国宝)に西方浄土への来迎を願うのが、お参りの方法とされています。
紅葉の頃はさぞかし!と思われる三重塔。
大きな九体の阿弥陀如来坐像も見事で、その四隅には国宝の四天王像も守護をしています。
九体寺と言う別名も持つ「浄瑠璃寺」は奈良のお寺とは言うものの、行政的には京都府・木津川市にあります。
山に囲まれた鄙びた里にひっそりとした佇まいで建っているのは昔も今も同じです。

山門までの道には萩の木が植えられ、多分もう少しで満開になるのでしょう。

中央の宝池を一周すると「鐘楼」や「石仏」たちもひっそりと木陰に隠れるように迎えてくれます。
浄瑠璃寺はJR奈良・近鉄奈良からも直行バスがありますが、JR加茂駅からも循環バスが出ています。
2009年05月06日
難波八阪神社
神社の前を通りかかった人は、鳥居の奥に異様に大きな獅子頭が見えるのでビックリすることでしょう。

阪神なんば線の開通で難波が近くなったので「難波八阪神社」に行って来ました。
ここの驚きは「獅子殿」の大きさです。

高さ12m、奥行き7m、幅7m。1974年に完成しました。
目はライト、鼻はスピーカーにもなっていて神事の舞台にも利用されます。
お参りの人と大きさを比べて見て下さい。

鉄筋コンクリート製、天井の鳳凰の彫刻はすべて手彫りです。

大きな口で勝利を呼び、邪気を飲み商運を招くと「就職」「入試」「会社発展」を祈願する人が多いそうです。

難波・八阪神社には計8組、16体の獅子狛犬が配置されています。
阿吽(あうん)の口元をして本殿の左右に安置されていますが、阿は「陽」で男性、吽は「陰」で女性。
獅子狛犬は本殿から見て左に「獅子」、右に「狛犬」が配置されてるのが普通だそうです。
(両方とも同じように見えますが・・・・)
八阪神社の後ろ足をあげた「かまえ型」(出雲型)獅子、ブロンズ製。

同じく狛犬。

民間信仰として「止事成就」のために獅子狛犬の足にコヨリを結び「禁酒」「禁煙」「受験すべり止め」祈願をするそうです。
大阪「難波八阪神社」 地下鉄・四つ橋線「なんば」下車 四ツ橋筋を南に「東横イン」の裏側
阪神なんば線の開通で難波が近くなったので「難波八阪神社」に行って来ました。
ここの驚きは「獅子殿」の大きさです。
高さ12m、奥行き7m、幅7m。1974年に完成しました。
目はライト、鼻はスピーカーにもなっていて神事の舞台にも利用されます。
お参りの人と大きさを比べて見て下さい。
鉄筋コンクリート製、天井の鳳凰の彫刻はすべて手彫りです。
大きな口で勝利を呼び、邪気を飲み商運を招くと「就職」「入試」「会社発展」を祈願する人が多いそうです。
難波・八阪神社には計8組、16体の獅子狛犬が配置されています。
阿吽(あうん)の口元をして本殿の左右に安置されていますが、阿は「陽」で男性、吽は「陰」で女性。
獅子狛犬は本殿から見て左に「獅子」、右に「狛犬」が配置されてるのが普通だそうです。
(両方とも同じように見えますが・・・・)
八阪神社の後ろ足をあげた「かまえ型」(出雲型)獅子、ブロンズ製。
同じく狛犬。
民間信仰として「止事成就」のために獅子狛犬の足にコヨリを結び「禁酒」「禁煙」「受験すべり止め」祈願をするそうです。
大阪「難波八阪神社」 地下鉄・四つ橋線「なんば」下車 四ツ橋筋を南に「東横イン」の裏側
2009年02月16日
新薬師寺
奈良・春日大社の少し南に位置する「新薬師寺」は本尊・薬師如来を取り囲む国宝・十二神将のお寺として有名です。
会いに行って来ました。

8世紀に造られた像をCGで色彩豊かに再現、戌年の守護神・バサラ大将。
日本最古で最大の十二神将立像は「見事!圧巻」としか言いようがない。
天平時代に造られた十二体の立像は色彩こそ剥げ落ちているが、表情や個性が豊かで観る者の心を揺さぶります。
http://www.k5.dion.ne.jp/~shinyaku/juunishin.html
バサラ大将 戌年
アニラ大将 未年
ハイラ大将 辰年
ビギャラ大将 子年
マコラ大将 卯年
クビラ大将 亥年
ショウトラ大将 丑年
シンタラ大将 寅年
サンテラ大将 午年
メキラ大将 酉年
アンテラ大将 申年
インダラ大将 巳年
手足の位置、武器の種類、髪の毛、姿態、それぞれ違った十二の像が十二支の守護神になり円形中心の薬師如来坐像を守っています。

酉年・メキラ大将だけが両手に何も持っていません。

この本堂の中に国宝像があります。
本堂前には「くろがねモチノキ」がたわわな実を付けて繁っていた。樹液は鳥もちの材料になるそうです。

奈良・新薬師寺の十二神将。ぜひご覧あれ!¥600
山門には「気をつけておかえ(る)り」と金と銀の蛙の置物が。皆に頭撫ぜ撫ぜされて剥げてました。

会いに行って来ました。
8世紀に造られた像をCGで色彩豊かに再現、戌年の守護神・バサラ大将。
日本最古で最大の十二神将立像は「見事!圧巻」としか言いようがない。
天平時代に造られた十二体の立像は色彩こそ剥げ落ちているが、表情や個性が豊かで観る者の心を揺さぶります。
http://www.k5.dion.ne.jp/~shinyaku/juunishin.html
バサラ大将 戌年
アニラ大将 未年
ハイラ大将 辰年
ビギャラ大将 子年
マコラ大将 卯年
クビラ大将 亥年
ショウトラ大将 丑年
シンタラ大将 寅年
サンテラ大将 午年
メキラ大将 酉年
アンテラ大将 申年
インダラ大将 巳年
手足の位置、武器の種類、髪の毛、姿態、それぞれ違った十二の像が十二支の守護神になり円形中心の薬師如来坐像を守っています。
酉年・メキラ大将だけが両手に何も持っていません。
この本堂の中に国宝像があります。
本堂前には「くろがねモチノキ」がたわわな実を付けて繁っていた。樹液は鳥もちの材料になるそうです。
奈良・新薬師寺の十二神将。ぜひご覧あれ!¥600
山門には「気をつけておかえ(る)り」と金と銀の蛙の置物が。皆に頭撫ぜ撫ぜされて剥げてました。