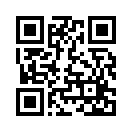2011年11月07日
吉備路を行く
岡山市の北、いわゆる吉備路に初めて行きました。
以前から「吉備津神社」には行きたかったのです。

岡山駅から吉備線と言う支線が出ていて割りに近いところにあります。
山門から本殿へは急な階段が。


吉備津神社の本殿は「国宝」です。

山の裾野にある境内はかなり広く、長い回廊で末社とつながっています。
回廊の中。


本殿と回廊の関係はこのようになっています。
ちょうど「七・五・三」の時期で、結構子ども連れの家族も大勢いました。
慣れない着物姿で裾を踏んで転んだ娘を父親が泥を払ってる微笑ましい姿も。

境内の大銀杏の木も丁度色づいて。

境内にある智恵や学問・受験の神様「一台社」

おみくじで合格祈願です。

桃太郎伝説のあるのが吉備津神社。ちゃんと鬼退治伝説も有り、ちなんだ社や旧跡もあります。

備中神楽面の一式。
境内には水の流れていない水車小屋もありました。

生憎のお天気でしたが、刈り取られずに放置された稲の向こうに本殿が幻想的な姿で見えていました。

神主さんに聞いて驚いたのですが、吉備津神社は3つあると言う。
備前の国にあるのが「吉備津彦神社」。備中にあるのが「吉備津神社」。そして福山の備後の国にも吉備津神社があると言う。
備前と備中は昔の国境を挟んであまりに近くにあるため、備前を彦神社にしたそうです。
直ぐ近くなので「吉備津彦神社」にも行きました。

吉備津神社の大銀杏の木に代わり、彦神社では平安杉がご神木として葉をつけていました。

こちらの本殿は国宝ではありません。

第七代孝霊天皇の第三皇子・大吉備津彦命が主祭神と言うから、確かに古代ゆかりの神社です。

本殿の内部。
さて、ここまで来たからにはと、風土記の丘にある備中国分寺まで足を延ばしました。
コスモスと五重塔。

柿食えば鐘がなるなり法隆寺・・・にも国宝・五重塔がありますが、国分寺の五重塔は重要文化財でした。
でも、きっちり実った柿が迎えてくれました。


備中国分寺の山号は「日照山国分寺」です。
まだ時間があったので、日本の三大稲荷と言われる「最上稲荷」(さいじょういなり)にも寄りました。

「伏見」「豊川」と並ぶ稲荷だけに再建された本殿は見上げるほど大きく、初詣や節分には押すな押すなの人がお参りするそうです。岡山で第一の人気だそうです。
でも昔の本殿のほうが雰囲気はありました。

こちらの稲荷の起源は1200年前。明治には神仏習合が許されたという特別な稲荷で、お寺でありながら高さ27mの大鳥居が
随分手前の平野に突然建って現れ驚かされます。
旧・本殿への登り道には、七十七の末社の碑が並び、いろんなご利益を詠っています。

そのお社版も旧本殿の周りには並んでいました。

でも「稲荷」だから、やっぱり狛犬ではなく「狐」でした。

吉備津神社 http://kibitujinja.com/
吉備津彦神社 http://www.kibitsuhiko.or.jp/
備中国分寺 http://www.city.soja.okayama.jp/kanko/kankochi/kokubunji.jsp
最上稲荷 http://www.inari.ne.jp/
以前から「吉備津神社」には行きたかったのです。
岡山駅から吉備線と言う支線が出ていて割りに近いところにあります。
山門から本殿へは急な階段が。

吉備津神社の本殿は「国宝」です。
山の裾野にある境内はかなり広く、長い回廊で末社とつながっています。
回廊の中。

本殿と回廊の関係はこのようになっています。
ちょうど「七・五・三」の時期で、結構子ども連れの家族も大勢いました。
慣れない着物姿で裾を踏んで転んだ娘を父親が泥を払ってる微笑ましい姿も。
境内の大銀杏の木も丁度色づいて。
境内にある智恵や学問・受験の神様「一台社」
おみくじで合格祈願です。
桃太郎伝説のあるのが吉備津神社。ちゃんと鬼退治伝説も有り、ちなんだ社や旧跡もあります。
備中神楽面の一式。
境内には水の流れていない水車小屋もありました。

生憎のお天気でしたが、刈り取られずに放置された稲の向こうに本殿が幻想的な姿で見えていました。
神主さんに聞いて驚いたのですが、吉備津神社は3つあると言う。
備前の国にあるのが「吉備津彦神社」。備中にあるのが「吉備津神社」。そして福山の備後の国にも吉備津神社があると言う。
備前と備中は昔の国境を挟んであまりに近くにあるため、備前を彦神社にしたそうです。
直ぐ近くなので「吉備津彦神社」にも行きました。
吉備津神社の大銀杏の木に代わり、彦神社では平安杉がご神木として葉をつけていました。
こちらの本殿は国宝ではありません。
第七代孝霊天皇の第三皇子・大吉備津彦命が主祭神と言うから、確かに古代ゆかりの神社です。
本殿の内部。
さて、ここまで来たからにはと、風土記の丘にある備中国分寺まで足を延ばしました。
コスモスと五重塔。
柿食えば鐘がなるなり法隆寺・・・にも国宝・五重塔がありますが、国分寺の五重塔は重要文化財でした。
でも、きっちり実った柿が迎えてくれました。
備中国分寺の山号は「日照山国分寺」です。
まだ時間があったので、日本の三大稲荷と言われる「最上稲荷」(さいじょういなり)にも寄りました。
「伏見」「豊川」と並ぶ稲荷だけに再建された本殿は見上げるほど大きく、初詣や節分には押すな押すなの人がお参りするそうです。岡山で第一の人気だそうです。
でも昔の本殿のほうが雰囲気はありました。
こちらの稲荷の起源は1200年前。明治には神仏習合が許されたという特別な稲荷で、お寺でありながら高さ27mの大鳥居が
随分手前の平野に突然建って現れ驚かされます。
旧・本殿への登り道には、七十七の末社の碑が並び、いろんなご利益を詠っています。
そのお社版も旧本殿の周りには並んでいました。
でも「稲荷」だから、やっぱり狛犬ではなく「狐」でした。
吉備津神社 http://kibitujinja.com/
吉備津彦神社 http://www.kibitsuhiko.or.jp/
備中国分寺 http://www.city.soja.okayama.jp/kanko/kankochi/kokubunji.jsp
最上稲荷 http://www.inari.ne.jp/
Posted by 李欧 at 18:37│Comments(0)
│古寺仏閣
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。