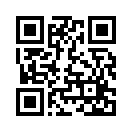2008年09月17日
日本一小さな動物園
池田市「五月山動物園」は日本で一番小さな動物園です。
それでも小さな子ども連れのファミリーで賑わっています。
入園無料。
ここの目玉は、池田市の姉妹都市オーストラリア・ローンセストン市から贈られた有袋類の「ウォンバット」。
生憎この日は庭に出て姿を見せてくれませんでした。
その代わり、池田駅前のサカエマチ商店街のキャラになってる穴掘り「ウォンバット」君をお見せしましょう。
ウォンバット以外にも動物はいます。あらいぐま。
小型のカンガルーの「ワラビー」。オーストラリアの強豪ラグビーチーム 「ワラビーズ」でも名前はお馴染み。
大きなネズミウサギ「マーラー」
小型のダチョウのような「エミュー」
こどもが直に動物と触れ合える「ふれあいコーナー」も有り、山椒は小粒でもピリリと辛い、と言うより心温まるZOOです。
参照:「さつきやまウォンバット物語」絵と文 川田敦子 40P ¥714 隣の案内休憩所で売ってます。
参照:HP http://www.ikedashi-kanko.jp/sub_page/meisyo_deta/meisho_zoo.html
せっかく池田まで来たのだからと町をぶらーっと散策しました。
池田と言えば落語「池田のシシカイ」、桂三枝師匠ゆかりの「落語みゅーじあむ」もちょっと有名です。
左党には「呉春」。酒蔵が外から見られます。
建物を見てるだけで美味しい肴と呉春が欲しくなりそう!
私も知らなかったけど「緑一」と言う銘柄があると言う「吉田酒造」。
吉田酒造の外観、呉春のすぐ近くです。
池田は「インスタントラーメン発明記念館」が有名で、他にも「逸翁美術館(閉館中)」や「池田文庫」「伏尾温泉」「ダイハツ本社」などもあります。
池田城跡公園の櫓。
2008年09月16日
萩の寺
豊中・曽根の「東光院・萩の寺」
萩まつり「道了祭」は~9月25日まで。
本堂前の白萩は見事。
仲秋の名月にススキは良く似合う。
元々大阪の中津にあった東光院は由緒ある古刹でした。
正岡子規が立ち寄って詠んだ句が句碑として残され、弟子の虚子なども立ち寄る俳句のお寺としても有名です。
「ほろほろと石にこぼれぬ萩の露」 子規
「於もひ於もひに坐りこそすれ萩の縁」
「我のみの菊日和とはゆめ思はじ」 虚子
明治35年9月19日、34歳で亡くなった子規を慕って弟子たちが供養した子規忌「へちま供養」。
旧暦の8月15日・中秋の名月の晩(今年は9月14日)に採ったへちま水は薬になるとの言い伝えがあり、東京・根岸の子規庵には今もへちまがぶら下がっています。
「をとといのへちまの水もとらざりき」
「痰一斗糸瓜(へちま)の水も間にあはず」
「糸瓜咲て痰のつまりし佛かな」 絶句
死の前日詠んだ3句が子規の絶筆でした。
萩の寺でも大勢の俳句ファンが集まってちょうど「へちま供養」句会が催されていました。
萩の庭には俳句の短冊もぶら下がっています。
行基ゆかりの萩の寺の歴史を見れば・・・・。
「日本人の美と心を象徴する「萩」は、秋の七草の筆頭として知られるが、行基ゆかりの草花でもある。その名前の由来は「生え木」に由来し、古来から生命力の強さや復活を象徴する。すなわち再生を意味する」と記されている。
東光院・萩の寺は、チベットの仏画や曼荼羅なども展示され、淀君ゆかりの「萩の小筆」なども売られていました。
また、中国の孫文も日本亡命中に一時かくまわれたと言うから、中津にあった頃はかなり大きなお寺だったのでしょう。
切花に適さない地味な花ではあるけれど、いかにも「仏」に相応しい萩。
そこはかとない人生の襞が見え隠れする萩。
猪・鹿・蝶の花札ではお馴染みだったけど、これだけいっぱい咲いてる萩を見ていると、ふと我が行く末など考えてしまいました。
東光院・萩の寺 阪急・宝塚線「曽根」下車 東北へ直ぐ。
06-6852-3002
2008年09月11日
おとなのBar Ⅴ
アーネスト・ヘミングウェイから名前を貰った「PaPa Hemingway」
カウンターの前には渋い表情のヘミングウェイの写真が3枚飾られています。

熟年より少し若い世代の客が多いのは、イケメン・バーテンダーの年齢のせいか、それとも1995年に開店したせいかも。
それでもお客への気遣いとサービスは行き届いています。
「パパ ヘミングウェイ」の晩夏の付き出しは「赤ピーマンのムース、トマトソースかけ」。夏バテの時期に嬉しい。

パパ・ヘミングウェイに因んでか、葉巻を吸うお客も多い。マスターもシガーアドバイザー認定資格を持つ。
これまで紹介した「おとなのBar」に関しては「嫌煙」とは程遠く、どこも大きな灰皿が置いてあるのが印象的。お酒には煙草が付きものだと言うことか。そして、ここでも灰皿に吸殻が2本程度溜まるとさりげなく交換してくれます。
マスターはヘミングウェイと言うよりむしろ優しい野武士と言う雰囲気。カウンターを挟んでお客とは一線を引いてるところがおとなのBarとして心地よい。

「パパ ヘミングウェイ」もやがては神戸の老舗バーの仲間入りをすることでしょう。
「サボイ」と同じ「第3天成ビル」2F 北野坂「そばの正家」の裏の筋。
Tel 078-391-2838 http://papahemingway.bar-kobe.net/
カウンターの前には渋い表情のヘミングウェイの写真が3枚飾られています。
熟年より少し若い世代の客が多いのは、イケメン・バーテンダーの年齢のせいか、それとも1995年に開店したせいかも。
それでもお客への気遣いとサービスは行き届いています。
「パパ ヘミングウェイ」の晩夏の付き出しは「赤ピーマンのムース、トマトソースかけ」。夏バテの時期に嬉しい。
パパ・ヘミングウェイに因んでか、葉巻を吸うお客も多い。マスターもシガーアドバイザー認定資格を持つ。
これまで紹介した「おとなのBar」に関しては「嫌煙」とは程遠く、どこも大きな灰皿が置いてあるのが印象的。お酒には煙草が付きものだと言うことか。そして、ここでも灰皿に吸殻が2本程度溜まるとさりげなく交換してくれます。
マスターはヘミングウェイと言うよりむしろ優しい野武士と言う雰囲気。カウンターを挟んでお客とは一線を引いてるところがおとなのBarとして心地よい。
「パパ ヘミングウェイ」もやがては神戸の老舗バーの仲間入りをすることでしょう。
「サボイ」と同じ「第3天成ビル」2F 北野坂「そばの正家」の裏の筋。
Tel 078-391-2838 http://papahemingway.bar-kobe.net/
2008年09月10日
備前焼
岡山県・備前市・伊部(いんべ)は備前焼の里として親しまれています。

青空に黒煙を上げて・・・どんな焼き物が出来上がるのかな?
「信楽」「立杭」に比べて高級なイメージが強い備前焼は、それでも人気は高い。
JR伊部駅を降りると直ぐ窯や工房が広がるので手軽に「焼きものの里 散策」が楽しめます。

狭い地区に固まってお店があるので、店選びはちょっと迷います。

個人的には陶器より磁気のほうが好きなので、購買意欲がない分、佇まいや雰囲気を楽しめました。
茅葺ギャラリーもあります。

これまで何度も伊部を訪れていますが、「備前焼は値段が高い」と感じるのは、その良さが分かってないからかも知れません。
10月18・19日には「陶器祭り」も開催されます。
http://www.touyuukai.jp/maturi.html
青空に黒煙を上げて・・・どんな焼き物が出来上がるのかな?
「信楽」「立杭」に比べて高級なイメージが強い備前焼は、それでも人気は高い。
JR伊部駅を降りると直ぐ窯や工房が広がるので手軽に「焼きものの里 散策」が楽しめます。
狭い地区に固まってお店があるので、店選びはちょっと迷います。
個人的には陶器より磁気のほうが好きなので、購買意欲がない分、佇まいや雰囲気を楽しめました。
茅葺ギャラリーもあります。
これまで何度も伊部を訪れていますが、「備前焼は値段が高い」と感じるのは、その良さが分かってないからかも知れません。
10月18・19日には「陶器祭り」も開催されます。
http://www.touyuukai.jp/maturi.html
2008年09月09日
牛窓
岡山県・瀬戸内市・牛窓は「ペンション」と「オリーブ」の町だと思ってたら、意外にも古い歴史ある町でもありました。
江戸時代には参勤交代の大名や朝鮮通信使が寄港し、往時の文化遺産も残されています。「海遊文化館」(元・警察署)や「街角ミュゼ牛窓文化館」(元・中国銀行)・「旧牛窓郵便局」などの洋館が「しおまち唐琴通り」に残ってます。
海岸沿いに細く伸びる「唐琴通り」にはこんな建物もあちこちに。
目の前は「前島」、その向こうに「小豆島」や四国の山並み。
「日本のエーゲ海」とパンフレットに書いてあるのはちょっと誇張かも知れませんが・・・・。
前島との間の狭い海峡「唐琴瀬戸」。
唐琴の瀬戸に立つ「燈籠堂」,航海の安全を見守って来ました。
狭い港町は尾道をぐっと縮小した感じ、到る所に焼き板塀の路地が見られます。
「本蓮寺」(室町時代建立)は三重塔を持つ古刹。唐琴通りの丘に建ち、朝鮮通信使の接待所でもありました。
「日本のエーゲ海」と呼ぶからにはやはりオリーブも重要な構成要因、ちゃんと「オリーブ園」もあります。
海岸通りのオリーブ並木には青い実もたくさんぶら下がってました。
ホテルのショップの「オリーブ製品」コーナー。
ヨットハーバー・ペンション・小奇麗なリゾートホテル、海・夕日・月光。
確かにカップルや女性たちが喜ぶ要素は充分揃っていて、実際、ファミリーやカップル、熟年女性グループが多く訪れていました。
でも、居酒屋がない、美味しい魚料理の店がない、アクセスが悪いなど、ネオン派ぐうたら男性客にとってはちょっと退屈な夜になるかも。
それでも「牛窓サンセット」は絵葉書のようでした。
2008年09月08日
備前おさふね
備前おさふね「刀剣の里」には「刀剣博物館」「今泉俊光刀匠記念館」「鍛刀場」そして「刀剣工房」がある。

「刀剣工房」で古い刀に磨きをかける砥ぎ師。
古い鞘を漆で補強している塗り師。

1300度の高熱で玉鋼を打つ鍛錬作業はこの日は見られなかったけれど、炉に火入れしているところは見られました。

守り継がれた匠の技が目の前で見られ、Q&Aも出来る「刀剣工房」は現代人には目新しい。
まだ300万本の日本刀が全国に散らばっていると言うから、この世界も広い。
「備前長船」と言えば「刀剣」の産地。時代の変遷とともに変わって来た形状や特徴なども丁寧に解説してくれます。
勿論、名刀の展示や「鞘(さや)」「鍔(つば)」の展示、「お土産物産館」も有り、なかなか興味深い施設でした。

JR赤穂線「長船」下車。ちょっと遠いけどタクシーなら800円くらい。
そして、同じJR赤穂線の日生(ひなせ)にはあまり知られていない「中南米美術館」があります。

日生で魚網の製造・販売をしていた故・森下精一氏のコレクションが中心で「マヤ文化」や「インカ文化」の収集品が展示されています。また、長寿の秘薬として「カカオ」が王に献上されていたとか、絵文字クイズなどちょっと賢くなる解説もあって面白い。


ミュージアム・ショップには中年米の小物のほか「百年の蜜」と言う竜舌蘭のシロップがあり人気商品になっています。私は同じ竜舌蘭でもテキーラの原料になる竜舌蘭から作った「百年の蜜」クリスタルを買いました。
日生と言えば「アナゴ」「岩ガキ」「シャコ」など海産物が有名で日帰りで仕入れに行く人も多いけど、海岸から5~6分のところに「中南米美術館」があると言うこと、初めて知りました。ただし日曜なのにお客は誰も居ませんでした。

「刀剣工房」で古い刀に磨きをかける砥ぎ師。
古い鞘を漆で補強している塗り師。
1300度の高熱で玉鋼を打つ鍛錬作業はこの日は見られなかったけれど、炉に火入れしているところは見られました。
守り継がれた匠の技が目の前で見られ、Q&Aも出来る「刀剣工房」は現代人には目新しい。
まだ300万本の日本刀が全国に散らばっていると言うから、この世界も広い。
「備前長船」と言えば「刀剣」の産地。時代の変遷とともに変わって来た形状や特徴なども丁寧に解説してくれます。
勿論、名刀の展示や「鞘(さや)」「鍔(つば)」の展示、「お土産物産館」も有り、なかなか興味深い施設でした。
JR赤穂線「長船」下車。ちょっと遠いけどタクシーなら800円くらい。
そして、同じJR赤穂線の日生(ひなせ)にはあまり知られていない「中南米美術館」があります。
日生で魚網の製造・販売をしていた故・森下精一氏のコレクションが中心で「マヤ文化」や「インカ文化」の収集品が展示されています。また、長寿の秘薬として「カカオ」が王に献上されていたとか、絵文字クイズなどちょっと賢くなる解説もあって面白い。
ミュージアム・ショップには中年米の小物のほか「百年の蜜」と言う竜舌蘭のシロップがあり人気商品になっています。私は同じ竜舌蘭でもテキーラの原料になる竜舌蘭から作った「百年の蜜」クリスタルを買いました。
日生と言えば「アナゴ」「岩ガキ」「シャコ」など海産物が有名で日帰りで仕入れに行く人も多いけど、海岸から5~6分のところに「中南米美術館」があると言うこと、初めて知りました。ただし日曜なのにお客は誰も居ませんでした。
2008年09月04日
四天王寺
大阪の「四天王寺」に初めて行きました。
仁王門では奈良の東大寺に次いで大きな金剛力士像(東西2体)がお出迎え。
南から順に「仁王門」「五重塔」「金堂」「講堂」と大きな建物が並ぶ「中心伽藍」は拝見料300円。
特に金堂のご本尊「救世観音菩薩」は優美で繊細です。
五重塔は上まで登れますが狭くて急な階段です。
山下摩起画伯の塔内壁画・釈迦三尊像。
回廊の中庭は玉砂利が敷きつめられ立ち入り禁止。
西部分にある龍の井戸。
回廊で囲まれた中心伽藍の外にも多くのお堂や院や伽藍があり、そのうち宝物館と本坊庭園は有料です。
平和ラッパ・日佐丸の漫才でお馴染み「天王寺の亀ノ池」も「石舞台」を挟んで健在。
たくさんの亀たちが泳いだり日向ぼっこをしてました。
「四天王寺ワッソ」や「天王寺舞楽」でお馴染みの四天王寺は町中にある総本山として多くの善男・善女が御参りしてます。
普通は四天王寺学園のある西側の「極楽門」から「転法輪」をくるくる回してから入ります。
大寺院・四天王寺の坂を西に下ったところが「新世界」。
心を清めて君子気分になった後で「さあ!遊ぶぞ!」
俗世の欲が待ってます。
2008年09月02日
浪花演歌の象徴

「王将」や「とんぼり人情」など浪花演歌の象徴・通天閣。
何度も改装され、綺麗になって今は地下に落語を聞く小屋も出来ました。
てっぺんのネオンの色は天気予報にもなっています。

通天閣の足元にある「さかな屋 六鮮」。梅田に比べて安くて新鮮なお寿司屋で店内も広くて清潔、職人の生きもいい。
「新世界」と聞くとちょっと敬遠する人もいるらしい。確かにおっちゃん・おばちゃんのセンスは神戸あたりと異なっているが、異センスを「新鮮」だと感じたり「面白い」と感じる感覚は大事です。
生活感そのものが分かる大阪下町独特の文化、それはまさしく「アジア」。
それはそれで悪くない。

表通りなのに、どことなく裏通りの雰囲気のある町並み。
流れ者らしきおっちゃんや段ボールおじさんも居る新世界。
台湾・中国・韓国人観光客が多い通天閣界隈。名物「串カツ」に「ビリケン」に「じゃんじゃん横丁」。
来年春には三宮⇒難波まで阪神電車で直行できることだし、ミナミや大ミナミはますます近くなることでしょう。