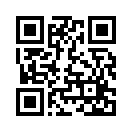2008年06月15日
芭蕉のふるさと
松尾芭蕉が三重県の伊賀上野の出身だとは知らなかった。

芭蕉の旅姿をイメージした「俳聖殿」。
総檜作りで堂々とした外観、お城のある「上野公園」にある。
伊賀・上野には何度も帰郷してるそうで、「芭蕉翁記念館」では
「芭蕉の帰郷から見えるもの」展を開催していた。

42歳 「野ざらし紀行」
43歳 「鹿島紀行」
45歳 「笈の小文」(須磨・明石にも来る)
45歳 「更級紀行」
46歳 「奥の細道」と、芭蕉は旅が多く紀行句集も多い。
51歳、大坂で亡くなるまで、熟年になっての紀行の跡が
記念館ではランプが点灯する日本地図で展示されていた。

それにしても、俳句と言えば「芭蕉」と言われるほど有名なのに、
もう少し派手で分かりやすい総合テーマ館にして欲しかった な。
伊賀上野の「芭蕉翁記念館」(昭和34年開館)はとっても地味で暗いのです。

芭蕉が24歳で詠んだこんな句は新鮮でした。
職員がPCで手作りしたのでしょう、
投句を呼びかける紙が壁に貼ってありました。
伊賀上野と言えばやはり「忍者屋敷」(伊賀流忍者博物館)
が有名で、同じ上野公園内にあるこちらは大入り満員。
芭蕉翁記念館が外人3人しか居なかったのと対照的。

入館料700円でからくり屋敷の説明付き、更に200円出せば
「忍者ショー」も見せてくれる。子ども用衣装は6,000円、それでも
多くの子どもが忍者の格好をして走り回っていた。
知人に「伊賀上野」の忍者屋敷と芭蕉の故郷の話をしたら
「ああ、では芭蕉も各地を巡って藩の実情を探る隠密だったんだね、納得!」
なんて、うがった見方をする人も居ました。芭蕉が実は隠密忍者!凄い翔んでる発想。

伊賀上野の上野公園一帯は「上野城」「だんじり会館」「忍者屋敷」
「俳聖殿」「芭蕉翁記念館」「上野歴史民族資料館」などが集まっている
観光地、観光バスも集まってました。
市内には他に「芭蕉生家」「蓑虫庵」「伊賀くみひもセンター」「伊賀越資料館」
などがあり、銀座通りと言う小奇麗なストリートには「伊賀牛」の肉屋も
あります。
最近、梅田から直通高速バスが6往復開設されました。90分1,500円。
御堂筋・旭屋書店前乗り場から。
芭蕉の旅姿をイメージした「俳聖殿」。
総檜作りで堂々とした外観、お城のある「上野公園」にある。
伊賀・上野には何度も帰郷してるそうで、「芭蕉翁記念館」では
「芭蕉の帰郷から見えるもの」展を開催していた。
42歳 「野ざらし紀行」
43歳 「鹿島紀行」
45歳 「笈の小文」(須磨・明石にも来る)
45歳 「更級紀行」
46歳 「奥の細道」と、芭蕉は旅が多く紀行句集も多い。
51歳、大坂で亡くなるまで、熟年になっての紀行の跡が
記念館ではランプが点灯する日本地図で展示されていた。
それにしても、俳句と言えば「芭蕉」と言われるほど有名なのに、
もう少し派手で分かりやすい総合テーマ館にして欲しかった な。
伊賀上野の「芭蕉翁記念館」(昭和34年開館)はとっても地味で暗いのです。
芭蕉が24歳で詠んだこんな句は新鮮でした。
職員がPCで手作りしたのでしょう、
投句を呼びかける紙が壁に貼ってありました。
伊賀上野と言えばやはり「忍者屋敷」(伊賀流忍者博物館)
が有名で、同じ上野公園内にあるこちらは大入り満員。
芭蕉翁記念館が外人3人しか居なかったのと対照的。
入館料700円でからくり屋敷の説明付き、更に200円出せば
「忍者ショー」も見せてくれる。子ども用衣装は6,000円、それでも
多くの子どもが忍者の格好をして走り回っていた。
知人に「伊賀上野」の忍者屋敷と芭蕉の故郷の話をしたら
「ああ、では芭蕉も各地を巡って藩の実情を探る隠密だったんだね、納得!」
なんて、うがった見方をする人も居ました。芭蕉が実は隠密忍者!凄い翔んでる発想。
伊賀上野の上野公園一帯は「上野城」「だんじり会館」「忍者屋敷」
「俳聖殿」「芭蕉翁記念館」「上野歴史民族資料館」などが集まっている
観光地、観光バスも集まってました。
市内には他に「芭蕉生家」「蓑虫庵」「伊賀くみひもセンター」「伊賀越資料館」
などがあり、銀座通りと言う小奇麗なストリートには「伊賀牛」の肉屋も
あります。
最近、梅田から直通高速バスが6往復開設されました。90分1,500円。
御堂筋・旭屋書店前乗り場から。
2008年06月15日
狸の里
滋賀県の信楽は町全体が狸でいっぱい!
どこを歩いても、どこを見ても、信楽焼きは「狸」しかないのか!と
思うくらい、徳利持ってブラブラさせた狸が歩いてる。
駅前の大狸、郵便ポストと大きさを比べて下さい。
滋賀県立「陶芸の森」。ここはちゃんとした企画展や展示も見られます。
陶芸の森のオブジェ「風の門」から見る信楽風景
町は道路も陶器が敷かれて観光客向けに工夫が見られる。
陶美通り。
炎美通り。
たぬきタクシーもあります。
町の通りには大小の陶器屋さんが並んでいます。
その殆どは狸の団体が向かえてくれるのですが、
中にはこんな小さなお店もあります。